『足の裏に影はあるか?ないか?』入不二基義 (著)
書評
執筆責任者:あんまん
本書を読み終わって、自分もこんな随想を書きたいと思った。本書は、哲学者である筆者の論文のようなある程度形式に制約がある書き方から脱却して、好きなことを好きなように書くという動機によって執筆されている。紙面には筆者の書くことの楽しさが滲み出ている。友達が隣で笑っていると、自分も釣られて笑ってしまうように、本書を読み進めると、その溢れ出る楽しさについ共感してしまい、読むのが楽しくなってくる。これほどワクワクしながら哲学的な考察を読んだのは初めてであった。だけど、本書のような魅力的な随想を書くには並大抵の言語運用能力では書ききれないだろう。それに筆者の鋭敏な洞察力、知覚力には驚かされる。例えば筆者は「とりあえず」という言葉に関心を持つ。「とりあえず」のあり方は、固定を確定へともたらすことなく、宙ずりにして開いたままにして、また、解れて弛んだ感じをもたらすという「とりあえず性」を抽出する。そこからさらに、時間の実在へと議論は発展してゆく様には、あまりの考察力の高さに私は脱帽してしまった。題名が「足の裏に影はあるか?ないか?」であるように本書で展開される議論はどれも卑近な事柄から始まる。だから難解な哲学書を読むときにありがちな、まず筆者が何を問題にしているのか分からないということはない。しかし、「とりあえず、ビール」とふだん何気なく使う言葉がどのような性質をしているのかに気を配るというのは、簡単に出来ることではない。それこそ筆者が幼少期からあれこれ物事を考えざる得なかったという哲学者がたいてい持ち合わせている狂気のようなものによって培われたものであろう。言葉に自覚的になると、その見え方も変わってくる。その発見がとても、心地よい。一度でもその経験をしてしまうと自分が使う言葉にむずむずして、いろんな言葉を確かめてみたくなる。
(768文字)
追加記事 -note-

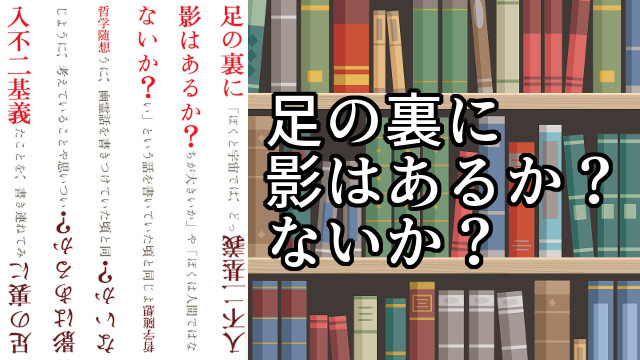




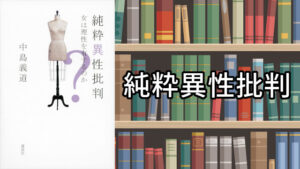



コメント