『物語 数学の歴史』加藤文元 (著)
書評
執筆責任者:蜆一朗
古代中国・メソポタミア・エジプト・ギリシアから始まり、つい30年ほど前に証明されたフェルマーの最終定理に至るまで、人類はその情熱・努力・天才によって壮大な数学の世界を切り開いてきた。本書では、その流れを解説する上で「西洋数学と東洋数学」という舞台設定を敷き、人間が「数学する」際に重要な行為として、形式的側面としての「計算する」ことと直感的側面としての「見る」ことの二つを挙げる。現代の立場から俯瞰的に見たときには、この「「計算する」ことと「見る」ことの統一」を西洋数学における永久のテーマと見なすことができる。数々の数学者たちが各自の問題意識のもとで葛藤を繰り返し、様々な苦悩を乗り越えた19世紀を経て、この試みは一つの大きな結実を見ることとなる。一方で我々日本の和算も含む東洋の数学は、爆発的な発展こそなかったものの、質的な面では西洋数学に引けを取らないほどの見識の高さを誇った。しかもその根底を支えたのは、何より数学を楽しもうとする高い精神であった。そして、現代の我々は、かつての東西の別を超えた「人類の数学」に到達した。本書はこうした数学の流れを、その深層にある思想的な側面に重点を置きながら、その中心を担った天才たちの人物史にも触れつつ、専門的な数学の内容をなるべく平易に噛み砕きながら解説する。推薦者は素人に産毛が生えたと言えるくらいには現代数学を学んだ経験を持っており、現代数学の難解な概念を本質を見失わない程度に事殺いで説明することの難しさを深く理解しているつもりである。その目から本書を見てみても、その説明の巧みさ、具体例が持つアナロジーとしての的確さと明快さ、用いられる語彙の豊富さが見事である。専門的に数学を学ばれた経験のない方にとっても、加藤氏の博覧強記ぶりや大らかさがありありと感じられると思う。数学や数学史に敷居の高さを感じておられる方にも自信を持って薦められる一冊だ。
(799文字)
追加記事 -note-




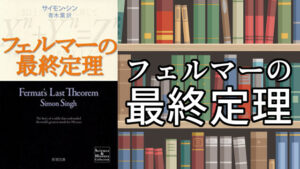



コメント